こんにちは、本日はコンクリートと塩分の関係について説明させていただきます。
新潟県は海あり県です。
沿岸部から50kmまでは塩害地域と指定されています。
錆びた自転車や給湯器などを目にする方も多いと思います。
これらは海が近いために空気中に含まれる塩分が多いことで起こる現象です。
わたしたち土木会社はもちろん、建設工事と切り離せない「コンクリート」も塩分には気をつけなくてはなりません。
・塩分の含有量を測定する「カンタブ試験」
・塩分が原因となるコンクリートのひび割れ「アルカリ骨材反応」
・住宅の基礎も!?塩害から基礎を守ろう。
カンタブ試験とは
カンタブ試験(塩分含有量試験)は、コンクリート用骨材や海砂の塩化物含有量を測定する試験です。
特に海砂を使用する場合、塩化物イオン量が0.04%以下であることが求められます。
試験方法は、骨材を温水で溶出させその溶液中の塩化物イオン濃度を硝酸銀滴定法などで測定します。
この試験は、JIS A 5308(レディーミクストコンクリート)の品質規格に定められており、塩害による鉄筋腐食を防ぐための重要な品質管理項目です。
近年は、自動測定器の導入により、より迅速で正確な測定が可能になっています。
アルカリ骨材反応とは
アルカリ骨材反応は、コンクリート中のアルカリ性物質と反応性を持つ骨材が化学反応を起こし、コンクリートにひび割れや膨張を引き起こす現象です。
特に問題となるのは、骨材中の反応性シリカ鉱物で、セメント中のアルカリ分と反応してゲル状物質を生成し、これが吸水膨張することでコンクリートを内部から破壊します。
塩分の存在は、この反応を促進する要因となります。
対策として、低アルカリ型セメントの使用や、反応性試験によって安全性が確認された骨材の選定が重要です。
また、定期的な目視点検でひび割れの早期発見に努めることも必要です。
住宅の基礎を塩害から守るには
住宅の基礎を塩害から守るためには、予防的な対策が重要です。
具体的には、まず配合計画の段階で水セメント比を55%以下に抑え、緻密なコンクリートを実現します。
鉄筋のかぶり厚さは一般的な環境下では40mm以上、塩害の影響が懸念される沿岸部では50mm以上を確保します。
また、防水性を高めるため基礎外周部には仕上げ材を施し、基礎周りの排水勾配を適切に設けて水はけを良くします。
特に海岸から1km以内の地域で心配な方は、防錆剤入りの混和材を使用するなどより積極的な対策が推奨されます。
以上、「コンクリート」と「塩分」には十分気をつけましょう!

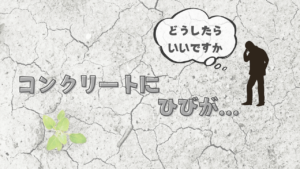
コメント